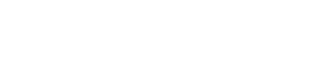令和7年度 生命論 夏季研修
2025年7月22日(火)~24日(木)
3年生の選択科目である生命論では、2泊3日で夏季研修を行っています。1日目は岡山県にあるハンセン病の療養施設である長島愛生園で研修、2日目は瀬戸内海に浮かぶ大久野島にある毒ガス研究所跡、毒ガス資料館を見学、3日目は広島平和記念資料館を見学した後、被爆者の方のお話を伺いました。
以下は生徒による振り返りです。
● 生徒による振り返り(こちらをクリック)
長島愛生園を訪れ、ハンセン病に関する基本的な知識から、その深い歴史、そして差別の実態について多くのことを学ぶことができた。見学前の事前学習が不十分だったことを反省すると同時に、現地での学びの重要性を実感した。今回は入所者の方に直接お話を伺うことはできなかったが、施設の方の説明を通じて、長島愛生園がかつて実際に多くのハンセン病患者の生活の場であったことを身に染みて実感した。生活や感情が想像しやすく、現実味をもって感じることができた。施設の中には、共同住宅のほかに小中学校・高校、グラウンド、礼拝堂、納骨堂などが整備されており、一つの町のような構造をしていた。入所者たちは、帰る場所がなく、そこに住み続けて一生を終えるしかない人たちが今でも暮らしている。
また、かつての患者たちは、歌舞伎や演奏会、囲碁・読書などの娯楽活動を行っており、舌読という口に本を当てて読む方法を使ってまで読書を続けていたことが紹介された。さらに、ハンセン病であることが知られたことで、本人だけでなくその家族までもが差別や迫害を受け、自分の名前すら名乗ることができなかったこと、子どもが発症した場合に、施設に送られる事実が家族に伝えられないこともあったこと、自分が発症しても関係のない身内が差別されたということの話があって、胸が痛くなった。政府は、ハンセン病が感染力の弱い病気であることを早い段階で把握していたにもかかわらず、長く隔離政策を続け、患者への差別や人権侵害を放置していた。その背景に何があったのか、なぜ隔離や消毒を続ける必要があったのかを考えてみても、納得できる答えにはたどり着かなかった。しかし、自分がもしハンセン病が危険な病気と恐れられていた時代に生きていたとしたら、正しい知識もなく、周囲に流されて患者を避けるような行動をとってしまっていたかもしれないとも思った。だからこそ、周りの意見や雰囲気に流されず、自分自身で確かめ、学び、それを信じて行動することの大切さを強く感じた。それを実行できるようになりたい。
園内の生活の様子は、思っていた以上に地域社会に似ていたからこそ、似ているのに違うという違和感が強く残った。これらの整った施設だからこそ「社会から切り離された暮らし」の重さがよりはっきりと感じられた。しかし、退所したり退所させられたり、逃走したり、人々の出入りが0ではなかったこともまた驚いた。辛い状況の中でも、野球チーム、愛生座(歌舞伎)や演奏会、読書などの娯楽を通して、なんとか自分を表現しようとする姿があったことに胸を打たれた。少しでも楽しみを見つけようとしていたことが分かり、驚きとともに、少し安心した気持ちにもなった。むつみ交流館から見た夜の海は本様に真っ暗で日中に感じた疎外感とは別の感情があり、真っ暗な世界に放り込まれたような入所者の人たちは感情になっていたかもしれない。帰りたくても帰れなかった人々、名前も名乗れず、誰にも知られないまま人生を終えた人がいると考えるとまた苦しくなった。誹謗中傷を与えていた側である、患者になったことがない市民は当時は誤解を事実だと思い込んで勝手な偏見で差別していた。それにもかかわらず時がたつと関心がなくなり、その誤解が解消されることなのないまま無関心になっていってしまったことが、今でも間違った知識を持ったまま思い込んでいしまっている原因にある。
これまで私は、広島といえば原爆投下の被害ばかりを思い浮かべ、それ以外の歴史についてはほとんど知らなかった。ゆえに、大久野島において日本が毒ガスを製造し、実際にそれを戦場で用いていたという事実を知ったとき、大きな衝撃を受けた。大久野島という名も、私は今回初めて耳にしたが、両親は「ウサギ島」として知っていた。この事実にも疑問が湧いた。なぜ、毒ガスと無関係に思えるウサギがこの島にいるのか。その違和感を胸に抱きながら、私は島へと渡った。かつてこの島では、従業員に誓約書を書かせ、島での活動を本州側から見えぬよう徹底的に秘匿していたという。十分な防具もなく毒ガスの製造に従事させられ、多くの者が後遺症に苦しんだ。戦後も、残された毒ガスは海や湖に捨てられ、土中に埋められ、いまだ完全には除去されていない。さらに、製造された毒ガスは戦地において、中国軍および一般市民に甚大な被害をもたらした。島内に今も残る倉庫や施設の跡を見れば、当時いかに大量の毒ガスが製造されていたかが明らかである。その量と被害の規模を想像するたびに、「なぜ、これほどのことがなされたのか」という重い問いが心に生まれた。すでに使われなくなった建物の静けさは、かえってその問いを深く響かせる。
現地のガイドの方によれば、大久野島周辺が地元の池田勇人元首相が、毒ガスの暗い記憶を消すために休暇村の整備を推進したという。確かに、毒ガスという言葉には負のイメージが伴う。だが、たとえ暗い過去であろうとも、それを無かったことにしてはならない。日本は原爆の被害を受けた「被害者」であると同時に、毒ガスを用いて多くの命を奪った「加害者」でもある。このどちらか一方の立場だけを知るのではなく、両方の歴史に真摯に向き合うことが、過去と向き合い、未来に責任を持つ姿勢につながるのだと感じた。
今回、広島の原爆資料館を訪れ、小学校6年生のときに行った時とは違う気持ちになった。事前学習で映画『太陽の子』を見ていたことで、単に「かわいそう」「ひどい」といった印象だけではなく、特に今回は、日本も実は原爆を作ろうと研究していたことを知った上で訪れたため、「もし日本がアメリカよりも先に原爆を完成させていたら、日本が他の国に原爆を使っていたのかもしれない」と、とても複雑な思いに駆られた。実際に日本でも1940年代に原爆開発が進められていたものの、資源や技術の限界で完成には至らなかったと知り、偶然や立場の違いだけで被害者・加害者の関係は変わるのだという人間の怖さも感じた。また、語り部さんのお話も心に残った。その方は1歳で被爆したため当時の記憶はほとんどなかったそうだが、その後の苦労や病気との闘い、被爆から60年経ってから急に原爆によるガンと正式に診断された話などを聞き、原爆の恐ろしさが「遠い昔の話」ではないことを実感した。言葉にならないほどの重みがあり、ただ「かわいそう」と共感するだけでは足りないこと、体験した人から直接聞くことで歴史のリアルさと伝えることの大切さをあらためて感じた。今回は、歴史の事実、戦争の残酷さ、そして人としてどう生きるかについても深く考えされられる貴重な機会となった。