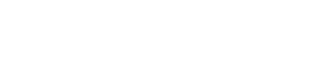穂谷(枚方市)の里山散策と農作業①
2025年4月20日(日)
桜が散るとともに、一気に暑くなってきました。その中で4月20日、田植えの時期にはまだ早いですが、我々は新年度1回目の穂谷へ訪れました。というのも今回は、穂谷一帯の土地の成り立ちや植生、それらを活用した「里山」を継承されている、本学元副校長の浅野淺春先生ほか有志の方々の取り組みを知るため、周辺の散策を兼ねて訪れたのです。
まずは集落のある場所から南へ。道すがら、穂谷の地質のお話や、手入れをして植物の群落を作られていることなど、さまざまなお話を伺いました。どれも浅野先生が 20年以上かけてなされてきたことなので、言葉に重みがあり、思わず感嘆の声をあげていました。同時に、自分はこれほど打ち込めるものを見つけられるだろうかと、少し考えてみたりもしました。
その後、東へ折れて谷を横切り、別の尾根に出るルートを取ったのですが…、もはやそこは「道なき草原」。背丈ほどもある草をかき分けて、少しずつ進みました。やっとの思いでそこを抜けると、尾根伝いに道を通り、山中にある朱智神社というお社に。名前すら聞いたことのなかった神社でした。が、話を聞くと、八坂神社ももとはここから分祀されたという、歴史と格式あるお社ということが分かってきました。その背景を知ってから見ると、格式を備えた荘厳さと人目を避けるような佇まいに、思わす息をのみました。
そんな朱智神社を後にし、尾根伝いに北上していると、浅野先生が道沿いにタラの芽の群落を発見されました。そこで、浅野先生の指導のもと、タラの芽を摘んでいくことに。トゲのある枝に悩まされながらも、皆で分け合えるだけの量を摘むことができました。(私の家ではおひたしにして頂きました。おいしかったです)
それを終えた後は、もとの集落へ戻り、少しばかり農作業を手伝ってから、帰途につくこととしました。
もともと私は自然環境について興味があったので、今回のお話は非常にためになるものでした。同時に、こうして振り返って文章を書いていると、こんなことを聞いておけばよかった、と少し後悔も。ともあれ、穂谷の成り立ちを知ったことで、次の田植えにもより深い気持ちで臨めそうです。
最後になりましたが、案内してくださった浅野先生、引率してくださった乾先生、ありがとうございました。
(文責:有志生徒代表)